青函トンネルは、日本を代表する海底トンネル。鉄道トンネルとして世界屈指のスケールを誇るその存在は広く知られていますが、実は「車でも通れるの?」「どこまでクルマで近づける?」「周辺に何があるの?」といった疑問を持つ人が少なくありません。この記事では、「青函トンネル」と「車」の関係をめぐるすべての疑問に答えながら、今まで知らなかった事実と視点を提供します。
そもそも青函トンネルとは?車で通れるの?
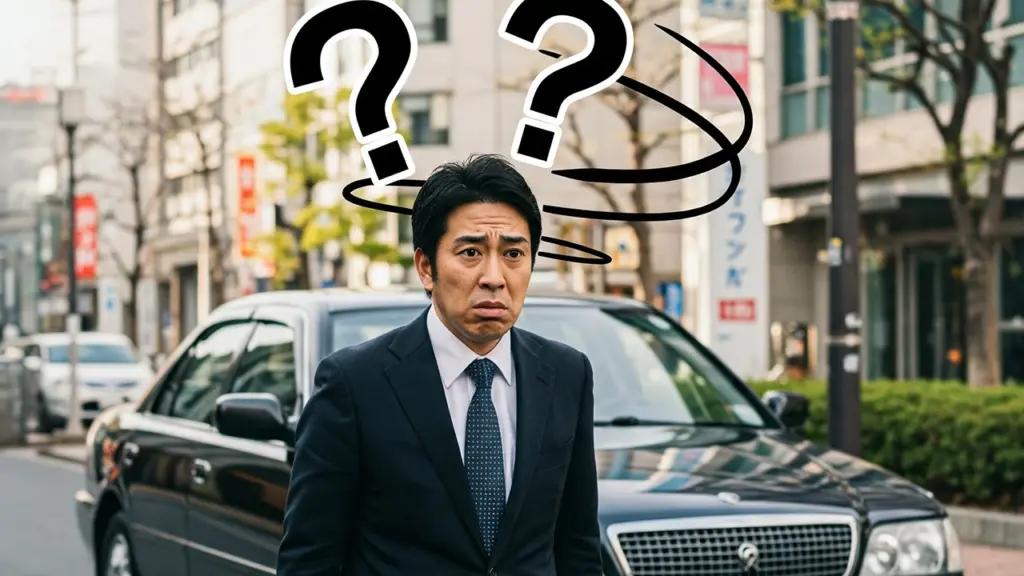
車について疑問を持っている人のイメージ
鉄道専用トンネルで、車は直接通れない
青函トンネルは、北海道と本州(青森)を結ぶ全長53.85kmの海底鉄道トンネルです。開通は1988年。トンネル自体は鉄道専用であり、一般の自動車が通行することはできません。これは自動車道路が併設されている青函道路トンネルのようなものは存在しないということです。
ただし、これには多くの人が誤解しやすい背景があります。
誤解を生んだ「防災代用車両」とは?
50系5000番代の客車を転用した青函トンネル用の防災代用車両は、非常時に乗客を救出・避難させるためのもの。「車」=「自動車」ではなく、鉄道車両の意味です。この誤解から、「車で通れる」という噂がネットで一部拡散されたこともありました。
じゃあ、車で青函トンネルに最も近づける場所は?
本州側青森県・津軽今別駅周辺
車で行ける最寄りポイントは津軽今別駅(奥津軽いまべつ駅)。駅周辺には駐車場もあり、新幹線利用者向けのアクセスは良好。ただし、駅構内やトンネル入り口付近は立ち入り禁止エリアが多いため注意が必要です。
北海道側木古内駅が最接近ポイント
北海道側では木古内(きこない)駅が拠点となります。こちらも車でアクセス可能で、「道の駅 みそぎの郷 きこない」と併設されており、観光にも適した立地です。
青函トンネル周辺を車で楽しむための観光スポット3選
青函トンネルを実際に通ることはできなくても、周辺には歴史や技術に触れられるスポットが満載です。
- 青函トンネル記念館(青森・竜飛)海底トンネルの仕組みや掘削技術を学べる展示が豊富。
- 道の駅 しりうち(北海道・知内)新幹線がトンネルに出入りする瞬間を眺められる展望スペースが人気。
- 津軽海峡フェリー車を船に積んで、函館⇔青森を移動する手段として最も現実的な「海上ドライブ体験」。
なぜ「青函トンネル 車」で検索する人が増えているのか?
最近、災害時の移動手段や物流の代替ルートとして青函トンネルに注目が集まっています。また、鉄道ファンや観光ドライバーの間でトンネルの周辺探訪が流行しており、「自動車でどこまで行ける?」「どうやって渡るのがベスト?」といった疑問が高まっています。
車で北海道と本州を渡る最適ルートは?
現状、自動車で本州⇔北海道を移動するには以下の2パターンがあります
- 津軽海峡フェリー青森〜函館間を結ぶ定期航路。車ごと乗船でき、所要時間は約3時間40分。
- 新日本海フェリー新潟・舞鶴などから小樽・苫小牧方面への大型航路。移動時間は長いが快適。
これらは青函トンネルの“裏ルート”として機能しています。車ではトンネルを通れないが、近づく・楽しむ・越える方法はしっかりあるのです。
実は奥深い!青函トンネルにまつわる「車」の歴史
50系車両が改造されて生まれた防災代用車両は、異常発生時の乗客退避や救助活動のため、青函トンネルの要所に待機していた特殊車両です。青20号で塗られたこの車両は、普段は目にすることのない存在で、鉄道の安全を守る影の立役者といえます。
マイクロエースから発売されるNゲージ製品は、そんな歴史を模型として再現したものであり、鉄道模型ファンにとっては非常に価値の高い逸品です。
車中泊やクルマ旅は楽しいですぞ!
本記事では、車中泊の知識的なお話しさせていただきました。
実は、私は趣味で日本各地を気ままにクルマ旅しているのですが、実際に現地に行った人しかわからない情報を無料で公開しています。
私が実際に日本各地を車中泊で巡ったときの体験談やその場所のレポートが見たい方は下記のURLに一覧で公開していますので、車中泊や地域の情報などが知りたい方はそちらをご覧いただければと思います!
また、インスタやYOUTUBEなんかもやってますので、そちらも合わせてご覧いただいて、面白いなとかもっと知りたいななんて思ったらフォローやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。
結論|青函トンネルと「車」の関係、もう迷わない
青函トンネルは車で通れません。しかし、その周辺には車でアクセス可能な場所や魅力的なスポットが多く、ドライブ旅行の目的地としても十分価値があります。また、海上フェリーを活用すれば、車での北海道・本州移動も問題なし。
そして、鉄道の安全を支えた防災代用車両や、鉄道模型という趣味の世界にまで広がるこのテーマは、ただの「通行可否」だけでなく歴史・技術・観光・模型文化の複合的な楽しみ方があるということを、ぜひ知っていただきたいのです。
今度、青函トンネル周辺を車で訪れるなら──この記事の視点を持って、「走れないトンネル」に新しい価値を見出してみてください。


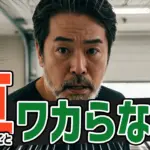
コメント